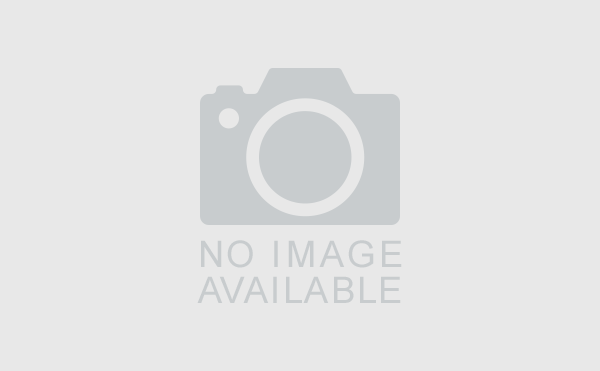ミツバチと情報伝達化学物質(セミオケミカルズ‐Semiochemicals)
はじめに
養蜂家なら誰でも知っているように、1匹のミツバチに刺された後は、引き続き攻撃されやすい。皮膚に残る刺針に付いている毒嚢から発散される匂い物質が、後続の蜂を惹き寄せるためである。
匂い物質は昆虫類にとって、我々の言語に等しいメッセージ伝達物質である。1959年、ドイツの研究者によって蚕から繁殖行動に関わる性フェロモンが発見されて以来、化学分析技術の進歩・機器の発展と共に、1000を越える数の昆虫フェロモンが見つかっている。
今日ではそれらの一部は合成され、もっぱら農作物や森林の害虫モニタリングの誘引剤として、あるいは彼らの繁殖行動を混乱させる環境保護型の農薬として実用化されている。
このように同じ種の個体間の情報伝達に関わる物質の外にも、現在、異種の昆虫の間にも重要な意味を持つ物質が次々に発見されてきている。(アレロケミカルズ=Allelochemicals.)
アレロケミカルズはその異種間の生物にもたらす影響の違いによって次のように分類されている。
アロモン(allomon) ------ 物質供給者に有益に、受給側の昆虫には無益または有害。
カイロモン(kairomon)---受給側昆虫のみに有益。
サイノモン(synomon)----両者に有益である場合。
セミオケミカルズとは、既知の各種フェロモンにこれらの全ての物質を加えたものを総称する。
ミツバチへの応用

ミツバチに関しては、近年多くの研究結果が発表され、産卵・育児・集合・警戒・分封などの行動のそれぞれに、それを制御する各フェロモンが存在することが知られている。なかでも女王蜂フェロモン(QMP—Queen Mandibular Pheromone)は、よく研究されていて実用化された製品が存在する。
QMPは女王蜂上顎から分泌される11種のフェロモン物質で、働き蜂の雌化(卵巣活性化)を抑えて、群の維持統率の中心の役割を果たしている。その内5種の成分を合成してミックスした製品(写真)がハウス栽培果樹の授粉用ミツバチに広く利用されている。無王状態の群に与えれば、長期間女王蜂の代わりを務めて働蜂産卵を抑え、群は正常に活動を続けるることができる。また分封群を誘引するため、これらの群を捕えるトラップとしても使われている。果樹への訪花促進剤として効果を狙うQMP製品も発売されたが、現在は製造が中止されている。
集合フェロモン(Nasanov Pheromone)は、働き蜂の尾端に近い第5節背板後方にある腺から分泌される7種の精油成分(Terpenoids)から成る。働き蜂が巣門付近で巣の方向に向けて頭部を下げて腹部を上げて旋風する様子はしばしば観察される。分泌腺を開放して空中に集合フェロモンを送り込んでいるのである。巣箱を内検した後や移動後、また女王蜂が交尾飛行に飛び立った後などには特によく観察できる。また群の女王蜂がなんらかの原因で失われた場合は、内検中に巣箱の内部でも大半の蜂が同じ行動を採る。ベテラン養蜂家であれば、旋風姿勢とひときわ高い羽音を察知して、すぐに無王群としてしかるべき処置を施すことになっている。
1882年にロシアの研究者Nasanov によって発見された当初は、1種の発汗行動と見られていたが、その後フェロモンの分泌発散であることが判った。分蜂群誘引剤として合成された製品も発売されたが、QMPと機能が重複して現在ではあまり出回っていないようである。
また、幼虫表皮から発散されるフェロモンも合成され、成蜂の訪花活動を刺激することが判り、製品が作られたが、メーカーの倒産により製造が止まった。
ミツバチヘギイタダニとセミオケミカルズ
ミツバチの育児巣房の中で産卵した母ダニとその成長した娘ダニは、蜂が羽化出房後は、すぐには封蓋前の5齢幼虫に再侵入せずに、一旦、成蜂なかでも育児日齢の蜂に好んで乗り移ることが知られている。ダニが他の日齢の働き蜂ではなく、育児蜂に強く引き付けられる要因は、ナサロフ腺分泌フェロモンのゲラン酸、ネロール酸の成分率の違いによるものと推測されている。
その後、母ダニは数日以内に、娘ダニは1週間余の成熟期間を経た後、蜂の幼虫表皮から出る数種の物質に惹かれて産卵のため再び巣房内に入り込む。脂肪酸エステル、パルミチン酸、炭化水素などを含む化合物が作用すると言われる。
封蓋された房室内でのダニの行動もまた化学的な刺激に依存している。特に蜂幼虫の繭形成期間中は、幼虫表皮に出る飽和炭化水素類に誘引される。
ダニが体内で卵子を形成して産卵できるためには、ダニは宿主のミツバチ幼虫の巣房室封蓋されてから12~24時間以内にミツバチ幼虫に接触しなければならない。しかし、単純に接触しただけで産卵が引き起こされるわけではない。実験では幼虫の抽出液がダニの産卵数を著しく増加させることが知られている。リンパ液の中に含まれる脂肪体の存在がその栄養源となると考えられる。
ダニに寄生された幼虫に対する成蜂の衛生行動(VSH行動)も嗅覚によって、引き起こされると推測されているが、その物質は未だ特定されていない。
ヘギイタダニのライフサイクルは、ミツバチのそれに100%依存している。すべての日齢において、これらの外にもさまざまな物質を利用していると考えられている。例えば、ヘギイタダニは雄蜂の幼虫巣房により好んで侵入する(2倍以上の寄生率)。ミツバチ雄の卵から羽化までの生育期間は働き蜂のそれより長く、ダニにとって雄蜂巣房は、より有利に繁殖できる場所になっている。
これにも雄蜂の幼虫体表から発散される匂い物質が関与していると考えられている。
ダニ駆除のためのセミオケミカルズの応用
誘引効果によるトラップまたは寄生行動に混乱を招くことができるかどうかという問題である。
この目的のためにいくつかのパテントが申請された中で、唯一Varoutestと呼ばれる製品が商品化されたが、野外テストの結果は満足できるものではなかった。研究によって、多くのフェロモン様物質が特定されたにもかかわらず、ダニのコントロールに使える道はまだ見つからない。
フェロモン物質を使っての害虫対策は植物食の昆虫に対しては多くの成功例があるが、同じ戦略はヘギイタダニには適用が難しいかも知れない。へギイタダニは宿主のミツバチのライフサイクルに100%適応する進化を遂げていて、その行動はミツバチの生理的な状態次第で変わることになる。
両者の関係は想像以上に複雑で、その間の化学的な情報伝達を完全に理解することは難しい。
結論として、この課題についての知識はまだ充分とは言えないし、ダニの生態もまだ完全に解明されているわけでもない。また仮にダニの生態に関与する化学物質の全体像が掴めたとしても、別の問題が解決される必要が生じて、ダニ対策にはつながらないかも知れない。
次のような事情が、この方法による駆除法の開発を難しいものにしている。
- ダニは羽化した蜂から育児バチの日齢の蜂へ、また育児バチから蓋掛け直前の蜂児に乗り移る瞬間以外は、その生涯を成蜂または蜂児の体表に寄生して過ごす。蜂児巣房への侵入にも、育児蜂が給餌のために巣房に頭を入れる瞬間を利用していると考えられる。ミツバチ自身がこれに加担していることになる。それゆえ、ダニをトラップする誘引物質が開発されたとしても、それ単独でダニの行動変化を引き起こすほどの影響を与えることができないかも知れない。
- ダニの産卵・交尾・生育を含めた繁殖過程が、外部から隔てられた封蓋房室の内部で行われるために、その物質をダニまで到達させることができない。
- 巣箱内に投与された化合物はミツロウによって吸収される可能性がある一方、揮発性のイオン化学物質はハチミツに吸着されてしまうかも知れない。
ヘギイタダニ駆除のためのセミオケミカルズの実用化はまだ先のことのようにみえる。しかし、実験室内でのYチューブ・オルファクトメーター(臭覚刺激装置)を用いたテストによって、ダニは明らかにこれらの物質の方向に向かうことが証明されている。特に繭形成が始まる直前の生きている5齢幼虫と育児日齢の蜂または冷凍保存の育児蜂には強く誘引されることも知られている。
ほぼ全ライフサイクルに多くのセミオケミカルズが関与している以上、ダニにピンポイントでかつ最も効果的な物質を作用させることは、決して不可能ではないと思われる。
チモールなど精油成分をを利用するダニ駆除法が一定の成果をあげている。ダニに対する直接的な駆除効果に加えて、強い匂いを巣内に充満させることで、基本的な行動を支配する匂い物質の判別を妨げて、混乱を生じさせているものと考えられている。さらなる研究が期待される。